会社を辞めたい。でも、辞める勇気が出ない。
そんな風に思いながら、毎朝、会社に行くだけで心と体が重くなる——。
もし今、あなたがそんな状態だとしたら、まず知ってほしいことがあります。
「身体に出ているサイン」は、心からのSOSかもしれないということです。
ぼく自身、かつて16年間、安定した職場に勤めていました。
ですが、その安定の裏側で、徐々に心と身体がすり減っていくのを、見て見ぬふりしてきたのです。
それを痛感したのが、ある年の出張先。
仕事が終わったあと、同僚と入った居酒屋で、突然「呼吸ができない」「お腹が苦しい」と感じ、立っていられなくなりました。
救急車を呼ぶような大事にはなりませんでしたが、あのときの体感は今でもはっきり覚えています。
まるで、脳が酸欠になっていくような、じわじわと意識が遠のく感覚。
でも、当時のぼくはこう思っていました。
- 「たまたま疲れてただけかも」
- 「寝たら治るでしょ」
その後も、懇親会や飲み会のたびに呼吸が苦しくなるなど、似たような症状が何度か起きました。
でも、そのたびに「まあ、気のせいだろう」と片付けてしまったんです。
そんなぼくに初めてブレーキをかけてくれたのは、当時付き合っていた今の妻でした。
「その職場、普通じゃないよ。あなたの体調も、おかしいと思う」
その言葉で、ようやく気づきました。
あれはストレスが限界までたまった“心からのサイン”だったのだと。
今のぼくなら、過去の自分にこう言います。
「さっさと辞めろ。我慢するな」
でも、あのときはそれができませんでした。
理由は「自分が弱いと思われたくない」「ここで辞めたら負けだと思われる」そんな無意識の思い込みでした。
…そんなぼくが、どうやって「辞める」という選択ができるようになったのか。
そのヒントを、この記事ではお伝えしていきます。
第1章:「心の不調」は、なぜ“後回し”にされるのか?

体調を崩したとき、多くの人が最初に考えるのはこうです。
「疲れかな」「寝れば治るかも」
頭痛や息苦しさ、胃の不快感——。
どれもよくある症状だからこそ、「まさか心のサインだとは思わない」のです。
ぼくも、かつてそうでした。
でも、それが「繰り返し起こる」ようになったら、ただの体調不良ではありません。
心が、何かに耐えきれなくなっている証拠かもしれません。
なぜ、心のサインは見逃されやすいのか?
理由はシンプルです。
- 目に見えないから
- 我慢できてしまうから
- 「頑張って当然」と思い込んでいるから
特に責任感の強い人や、周囲の目を気にしやすい人ほど、
「自分よりも、周りに迷惑をかけないこと」を優先してしまいます。
でも、そうやって“自分の心”を後回しにしてきた結果が、
「呼吸が苦しくなる」「涙が止まらない」「会社の前で足がすくむ」
そんな身体の異変となって現れるのです。
心の不調は、いきなりは来ない
これは、いきなり心が壊れるのではなく、
じわじわと“異変”が積み重なっていった結果です。
たとえば、こんなことはありませんか?
- 仕事のあと、何もしていないのに疲れ切っている
- 休日に「何もしたくない」気持ちが強くなってきた
- 朝の支度中、会社のことを考えると胃が重くなる
これらはすべて、「まだ動けるけど、実はギリギリ」の状態。
ストレスや不安が、身体を通して表面化しているのです。
心の異変に“気づける人”が強い
だからこそ、「サインに早く気づける人」こそが、自分を守れる人です。
「弱さに気づける人が、本当は強い」
そんなふうに、考え方の前提を変えることが、すべての始まりになります。
実際、ぼく自身も「辞める決断」ができたのは、
自分の心と体の限界を、ようやく“事実として受け入れた”あとでした。
第2章:「あの時の異変」が教えてくれていたこと
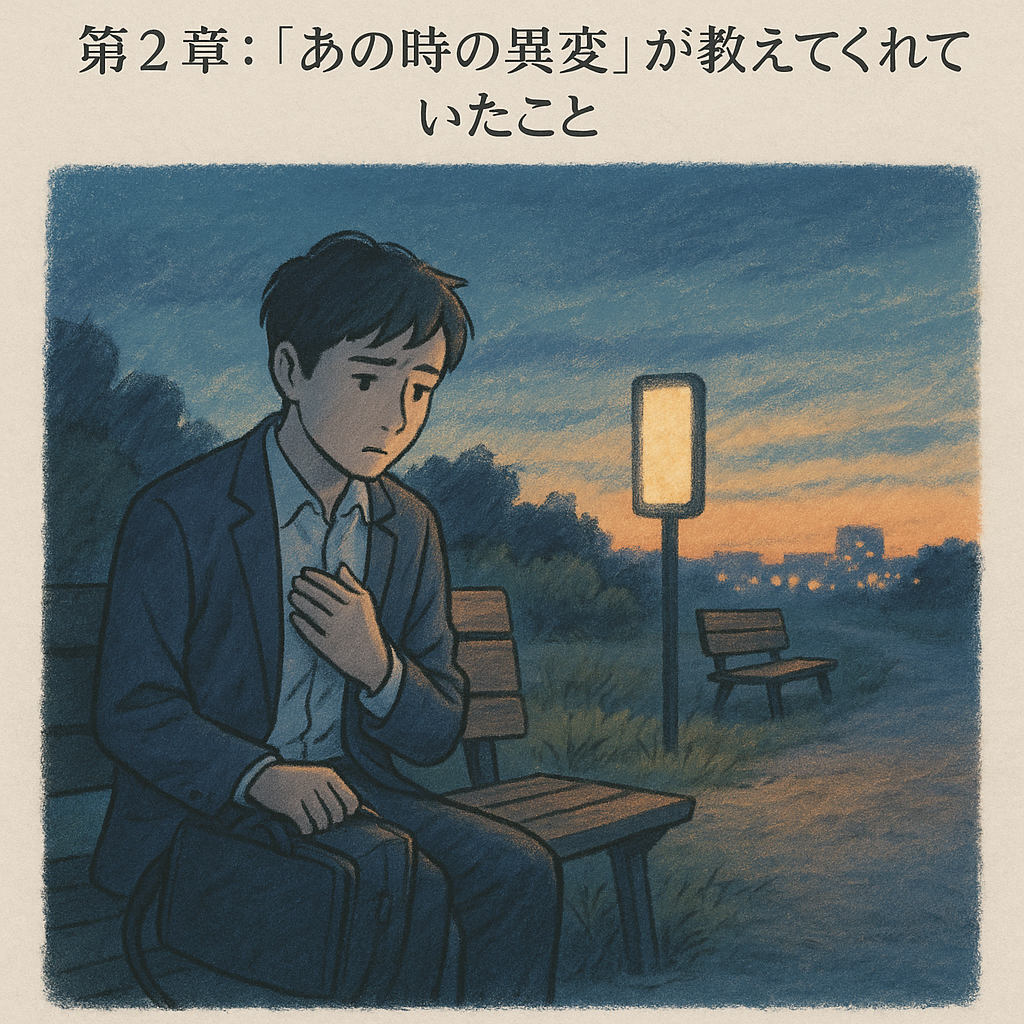
心や体の不調は、必ず何かの“サイン”として現れます。
ただしそのサインは、多くの場合「ふだん通りに生活できてしまう」レベルで訪れます。
だからこそ、「たまたまだろう」「気のせいかな」と無視してしまう。
でも、異変はちゃんとあなたに語りかけています。
「もう限界が近いよ」「これ以上、無理しないで」と。
ぼく自身が“倒れた日”のこと
正直に言うと、ぼくは動悸こそ出なかったものの、
出張先の居酒屋で、呼吸が苦しくなって倒れたことがあります。
お腹が締めつけられるように苦しくて、
吸っても吸っても酸素が入ってこない。
「このまま呼吸止まったらどうしよう」と思いました。
でも、その時は深く考えませんでした。
- 「疲れてたんだろうな」
- 「風邪気味だったのかな」
そうやって、“何かのせい”にして、見なかったことにしたんです。
今思えば、それは完全にストレスから来るサインでした。
妻(当時は彼女)に言われてようやく、
「職場での人間関係が、異常だったのかもしれない」
と気づいたのです。
“サイン”に鈍くなる理由
なぜ、ぼくらは自分のサインに気づきにくいのでしょうか。
それは、日々「我慢」を重ねすぎているからです。
小さな違和感に“慣れすぎて”しまっているからです。
- 「しんどいけど、みんなも我慢してるし…」
- 「ストレスって、こんなもんじゃない?」
- 「自分が甘えてるだけかもしれない」
そんなふうに考えて、どんどん“感度”が鈍くなっていく。
気づいたときには、もう立ち上がれないほど心がすり減っている。
——それでは、遅いのです。
サインを“ちゃんと受け取る”という選択
今のあなたにできることは、「サインに気づく練習をする」ことです。
それだけでいいんです。
- なんか最近、寝ても疲れが取れない
- 胃腸の調子がずっとおかしい
- なぜか職場の近くに行くと、足取りが重くなる
これらは、ただの体調不良じゃないかもしれません。
心からの“訴え”かもしれません。
だからこそ、
「今の環境が厳しすぎるだけかもしれない」
「もしかすると、自分を守る時期なのかもしれない」
そんなふうに、一歩引いた視点で見てあげてください。
第3章:「行動できる人」と「止まってしまう人」の分かれ道
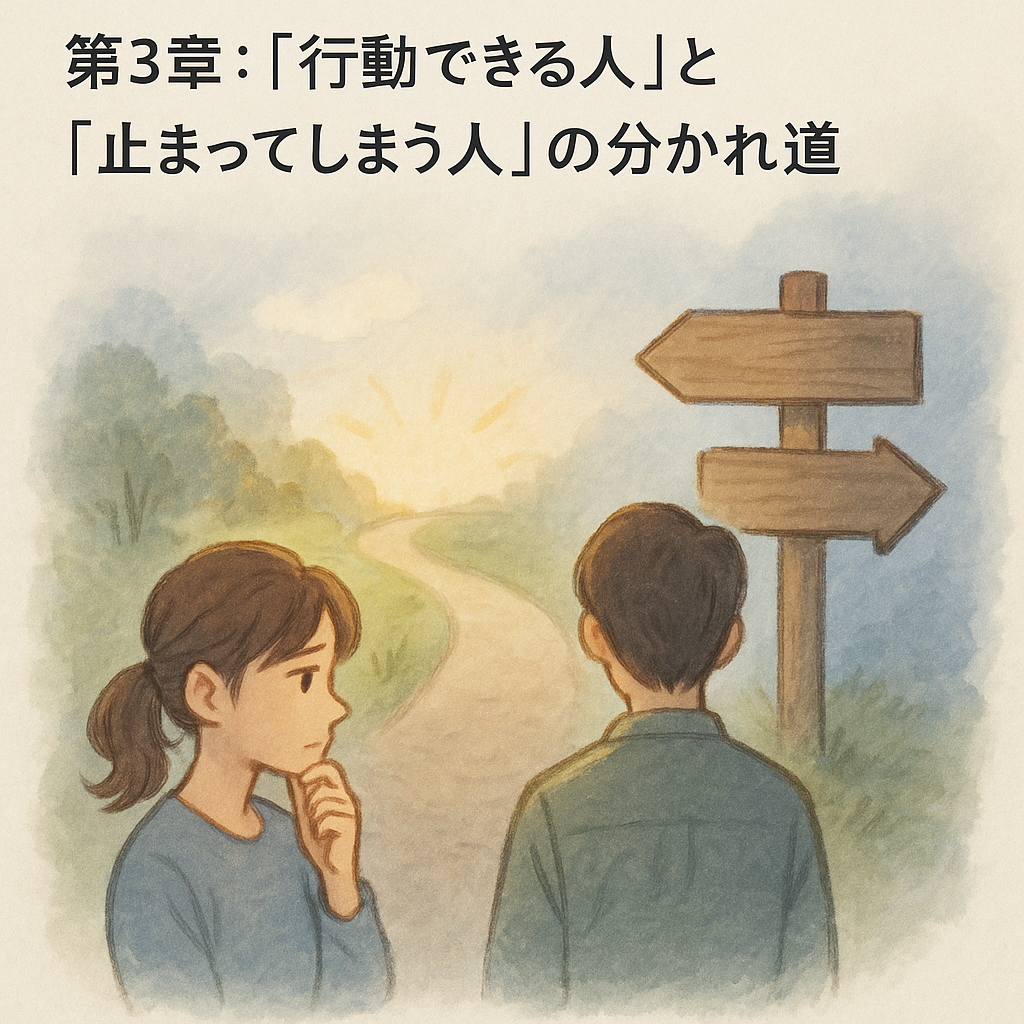
「やらなきゃ」と思っているのに、どうしても動けない。
そんなとき、よく「自分には行動力がないんだ」と責めてしまう人がいます。
でも、行動できるかどうかは「性格の問題」ではありません。
仕組みの違いなんです。
動ける人は、意志が強いわけじゃない
まず最初に強く伝えたいのは、
「行動できる人=意志が強い人」ではないということ。
行動できる人の多くは、「行動しやすい状態」をあらかじめ整えています。
たとえば、こんなふうに。
- あらかじめ予定に「10分だけやる時間」を入れておく
- やるべきことを「超具体的な単位」にまで分解する
- 環境を変えて、選択肢を減らす(誘惑を断つ)
つまり、“やる気”に頼らずに済む仕組みを持っているんです。
逆に、気合と根性だけで乗り切ろうとすると、
どこかでガス欠を起こしてしまいます。
「心の安全基地」があると動きやすい
もう一つの共通点は、逃げ道が確保されていることです。
「もしダメでも、戻ってこれる」
「今は失敗してもいい」
そう思える“心理的な余白”がある人ほど、行動を起こしやすい。
あなたにも、少し思い返してみてほしいんです。
何かに挑戦できたときって、「背中を押してくれた人」がいたり、
「失敗しても責めない場所」があったりしませんでしたか?
それがあると、人は“動いてみよう”と思えるんです。
「最初の一歩」を設計する
行動には“慣性”があります。
止まっているものは止まり続け、動いているものは動き続ける。
だからこそ、最初の一歩が一番大きなハードル。
ここでやるべきことは、たった一つ。
「小さすぎて笑えるレベルの一歩」を決めて、実行すること。
- 気になる求人を、1つブックマークしてみる
- 転職サイトを開いて、3分だけ眺めてみる
- 紙に「辞めたい」と1回だけ書いてみる
この程度でOKです。
それだけで、脳は「変化しても大丈夫かも」と感じはじめます。
あなたの“今”が、未来をつくる
ぼく自身、すぐに動けたわけじゃありません。
副業で最初の1円を稼ぐまでに7ヶ月以上かかりました。
SNSに投稿するだけで、手が震えることもありました。
でも、それでも進めたのは、「行動できる環境」と「小さな一歩」を作っていたから。
あなたにも、必ずその力があります。
第4章:やる気は続かない。でも、仕組みは続く
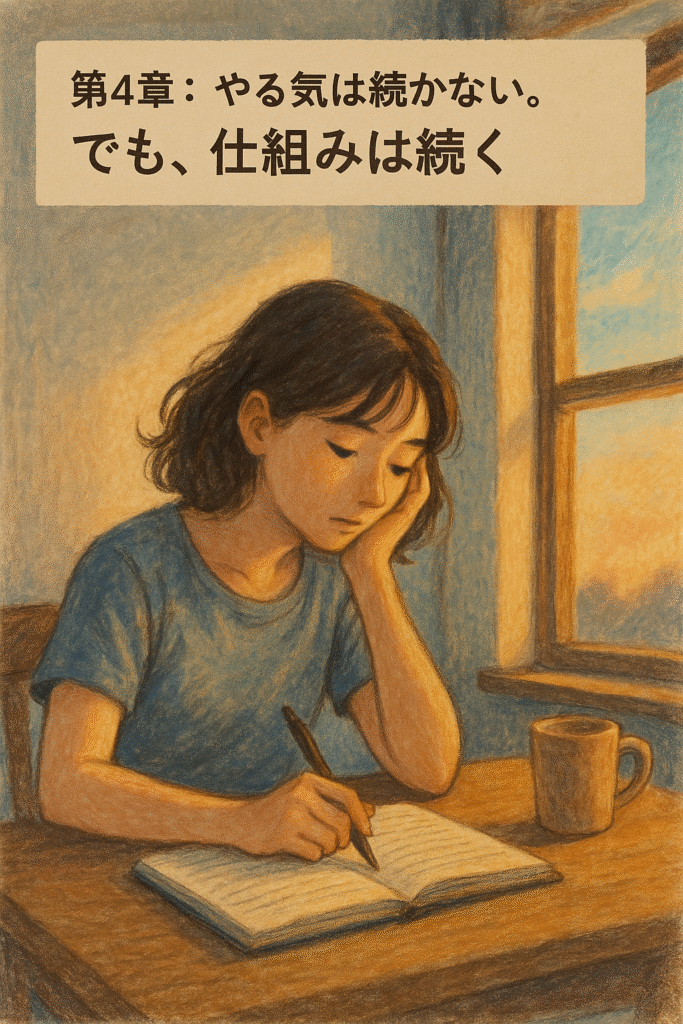
「今日こそ動こう」と思っても、気づけば1日が終わっていた。
そんな経験、ありませんか?
その問題点は、あなたの意志が弱いのではなく、
「やる気に頼っている」こと自体なのです。
継続に必要なのは「感情」じゃなく「設計」
たとえば、毎朝歯を磨くときに
「今日はモチベーションが高いから磨ける!」なんて思いませんよね。
「起きたら歯を磨く」という流れが決まっているから続くんです。
習慣とは、まさにこの「自動化の仕組み」そのもの。
“やる気”という不安定な燃料ではなく、
“仕組み”という土台を整えたほうが、結果的に行動が続くのです。
習慣化を支える3つの工夫
では、どうすれば行動を「習慣」に変えられるのでしょうか?
ここでは、ぼくが実際に使って効果があった3つの工夫をご紹介します。
① ハードルをバカみたいに下げる
「毎日30分勉強」ではなく、「1日1ページだけ読む」
「毎週転職サイトに応募」ではなく、「1日1回見るだけ」
このレベルでOK。
小さく始めれば始めるほど、継続率は上がります。
② すでにある習慣にくっつける
「歯を磨いたあとに求人サイトを見る」
「コーヒーを入れてる間にメモを書く」など、
既存の習慣に紐づけると、忘れにくくなります。
③ 記録する(だけでOK)
「今日は〇〇をやった」と手帳やメモに残す。
成果じゃなくていいんです。
「行動した」ことを見える化すると、自然と続けたくなります。
習慣化できない人の落とし穴
「三日坊主なんです…」という人に多いのは、
最初から完璧を目指してしまうパターンです。
「副業で月10万円」と意気込んで、
いきなり難しいことを詰め込もうとして失敗する。
まずは「1円でも自分で稼いでみる」くらいが、ちょうどいいんです。
続けることが、「辞められる自分」をつくる
少しずつ、自分の中に「変われた」という記憶が積み重なると、
不思議と、自信も未来の選択肢も広がっていきます。
ぼく自身、習慣の力で、
「怖くて辞められなかった自分」から「自分の人生を選べる自分」へと変わりました。
そしてこの変化は、才能ではなく設計の力で生まれたものです。
第5章:「辞めたら終わり」じゃない。「辞めた先」から設計する

「この先どうなるか分からないから、やめられない」
そんな声を、何度も聞いてきました。
でも実は、「辞めた後」が見えてくると、
“辞めるかどうか”を冷静に考えられるようになるんです。
ぼくも最初は、不安しかなかった
かつてのぼくも、「辞めたら地獄になるかもしれない」と思っていました。
収入は? 生活は? まわりの目は?
ひとつも答えなんて見えなかった。
でもある日、「辞める前提」で未来を組み立ててみたんです。
すると、不思議なことが起きました。
急に「自分の選択肢」が見えてきたんです。
設計を始めると、不安は「設計項目」になる
未来の不安は、放っておくと“漠然とした恐怖”になります。
でも、「書き出して」「分解して」「選択肢を持つ」と、
それは「設計できる課題」に変わるんです。
- 収入の不安
→ 固定費を洗い出す → 最低生活費を確認 → 副業収入や退職金と照らす - 評価されない不安
→ どんな仕事なら自分の強みを活かせそう?
→ 小さな実績をSNSやブログで積む - 孤立する不安
→ 信頼できる人・コミュニティ・学びの場を確保する
こうして1つ1つ書き出していくと、
「辞めたらヤバい」が「こう準備すれば何とかなる」に変わります。
“今の場所”からは、未来が見えにくい
辞めたいと思っているときって、
頭が「今のしんどさ」でいっぱいになっています。
その状態で未来のことを考えようとしても、
どうしてもネガティブな想像ばかりが浮かんでしまう。
意識的に“未来の視点”をつくることが大切です。
- 辞めたらどうなりたい?
- 何を得たい? 何を手放したい?
- そのために、今日できる準備は?
「辞めるかどうか」は置いておいて、
まずは“その先”を描いてみてください。
あなたが選ぶ未来に、正解も不正解もない
人生において、選ばなかった道の「正解」なんて、誰にも分かりません。
でも、「こうありたい自分」の輪郭が少しでも見えたとき、
人は“今いる場所”の選び方すら変わっていくんです。
- 「辞めても生きていける」
- 「辞めたら次はこう動こう」
- 「辞めずに続けるなら、こう整えていこう」
そんな風に、「選べる自分」になってほしい。
それが、この記事でぼくが一番伝えたいことです。
第6章:あなたの“一歩”が、人生を動かす
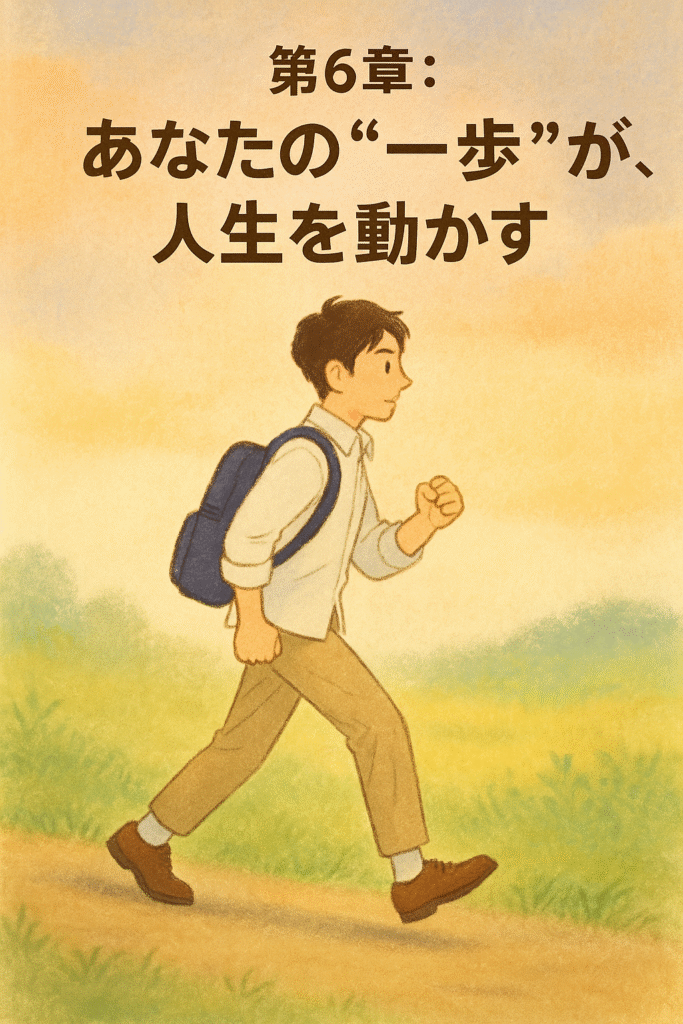
ここまで読んでくださって、本当にありがとうございます。
「やめたい。でも動けない」
その苦しさは、他人にはなかなか伝わりません。
でもぼくは、自信を持ってこう言えます。
今のあなたは、もう“変わり始めている”んです。
なぜなら、行動しようとしたから。この記事を開いたから。
そして最後まで読もうとしてくれているから。
「一歩」とは、なにか特別なことじゃない
- 転職サイトを開いてみる
- 紙に「辞めたい」と書いてみる
- 職場で嫌だったことを、そっとメモする
こんな行動だって、十分すぎるほどの「一歩」です。
大切なのは、「行動できない自分を否定しないこと」。
「よくここまで頑張ってきた」と自分に言ってあげてください。
人生を変えるのは、「すごい決意」じゃない
ぼくが辞めたときも、完璧な準備はありませんでした。
収入は不安定、スキルも不十分。
それでも動けたのは、「小さな選択」を重ねてきたからです。
- 「辞めたい」と思っていい
- 「しんどい」と言っていい
- 「変わりたい」と願っていい
「動けなくてもいい」んです。
ここから先の“深い悩み”には、別の準備が必要です
この記事では、「やめたいけど動けない」状態を
“自分のせいにしない”ための視点とステップをまとめてきました。
でも、いざ「辞める/続ける」を選ぶ段階になると、
ぶつかる悩みはより具体的かつ深くなっていきます。
- 辞めたあと、何をすればいいのか?
- 本当に生活していけるのか?
- 失敗したらどうする?
そんな“次の壁”を超えるヒントは、
noteにまとめています。
気になる方は、こちらから続きを読んでみてください。
会社を辞めたくてもやめられない人の最初の一歩を踏み出せるような記事です。
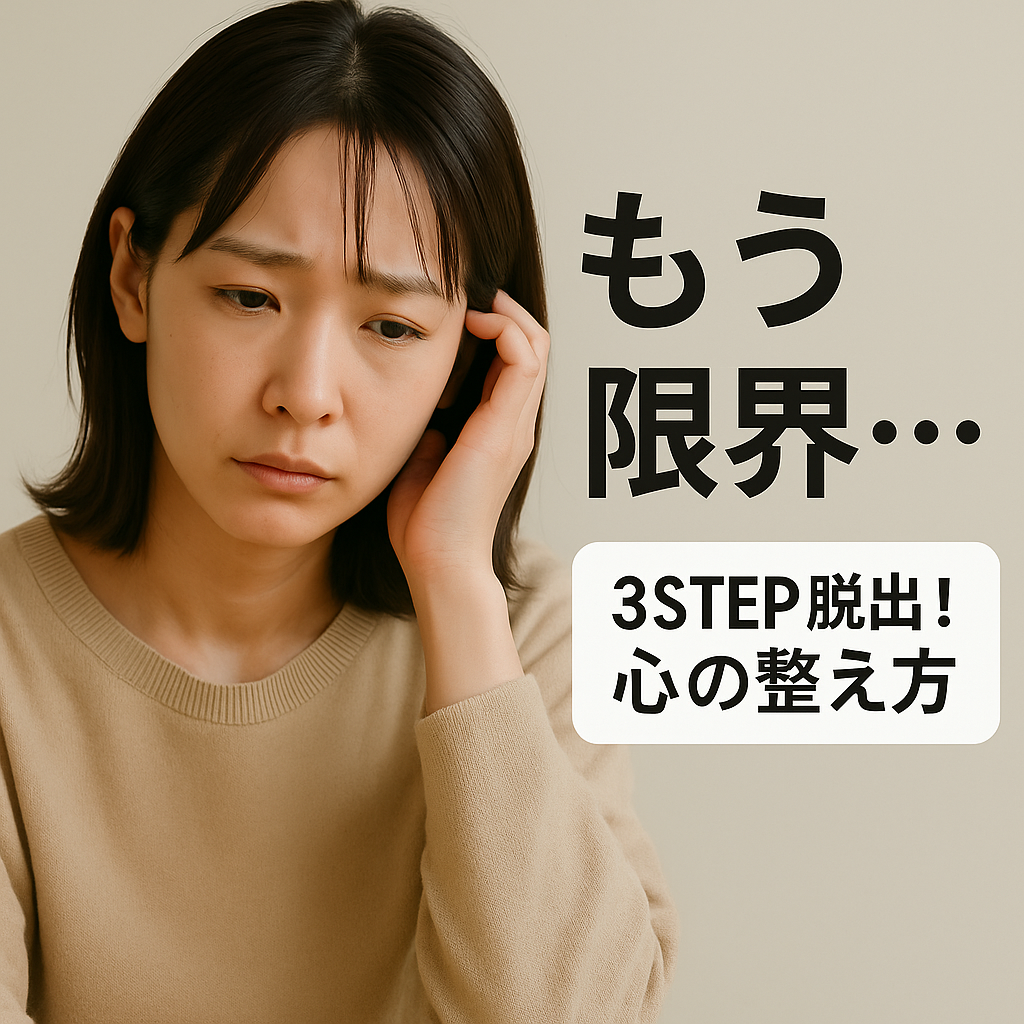
辞めたいのに辞められないあなたへ。「辞めてもいい」と思えたら救われた僕の話
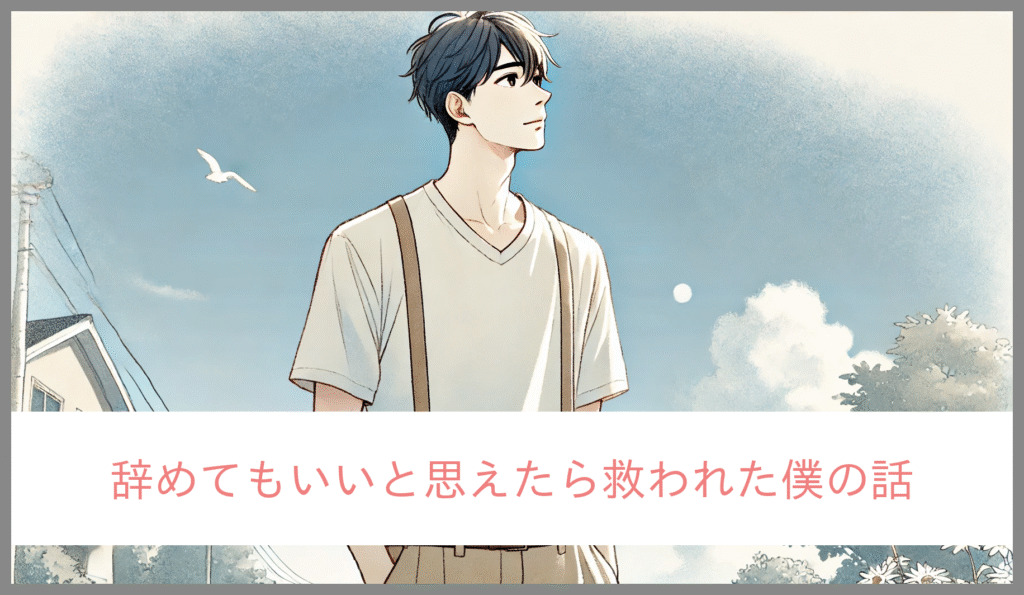

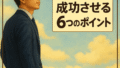
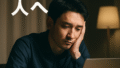
コメント